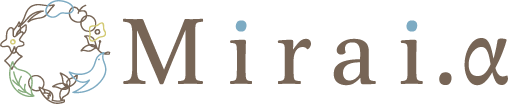「息子が不登校になってしまった…」そのとき

皆さま、こんにちは。代表のMaru.です^^
今回は、私の息子が不登校になったときの状況と、私の気持ちがどんなだったかをお話ししたいと思います。
【息子の不登校】
私の息子は、高IQと発達障がいを併せ持つギフテッド2E。
「IQが高いなら心配ないじゃない」
そう思われがちですが、実は、全然違います。
発達の凸凹がより激しく、思考レベルは高くても、
実際の自分は年齢相当もしくはそれ以下でしか行動できないという矛盾を常に抱えています。
例えば、家族以外の方と話すとき、息子の言いたいことは大抵伝わりません。
難しい言葉はたくさん知っている…でも、最も適当な言葉を必要な時に思い起こせない、幼い自分。
さらに、実際には高尚なことを言っていても、伝え方が簡略すぎて、周りは理解できない。
小さなトラブルが起きた後は、「だから僕は、こうするとこうなってしまうよって先生に伝えたんだけど…」と
自分の言葉が伝わらないことに対して、常に無力感を抱えていました。
そして、物事の捉え方が「普通」とは全く異なる息子ですから、
「普通」は分からないことが分かり、「普通」は当たり前に分かることが分からない。
年長さんに進級すると、息子は毎日のように「先生に怒られた…」としょぼんとして帰ってきました。
就学後に困らないようにという大人の計らいも虚しく、指導方法の変化に適応できなかった息子は、
なぜこれまで優しかった先生が急に怒るようになったのか理解ができず、恐怖だけを抱くようになりました。
さらに、発達特性上の感覚過敏と感覚鈍麻があり、非常に風邪をひきやすく、一年の半分は体調不良。
体調が悪いと大人でさえ不安になりますが、子どもであればなおさら。
集団の中で「自分の言葉が伝わらない」「自分を理解してもらえない」ことに不安を感じ、
私から離れることがどんどんと難しくなっていきました。
それまで楽しそうに行っていた習い事にさえも、私と離れることができず、次第に行けなくなりました。
小学校に入り、最初こそなんだかんだ興味が勝ったものの、興味が薄れた1年の7月以降はお休みを繰り返すように。
年長さんから始まって3年間、不登校の状態です。
—————————————————————
【私自身の気持ち】
私は、息子が赤ちゃんの頃から「発達障がいだろうなぁ」と思って育ててきました。
診断を受けたときも、「やっぱり」というだけで、特段それ以外にはなにも思いませんでしたし、
年長さんで登園拒否が生じたときには、おそらく不登校になるだろうことも予想できていました。
それでも、目の前にいざ「不登校」という現実が差し迫ると、親としての強い葛藤が生じます。
このまま6年間、いや中学まで…いや、高校まで、
いや、このまま永遠に引きこもりになるのではないか…
そういう思いが強く芽生え始め、不安と恐怖に陥りました。
「無理して行かせれば、心にもっと深い傷を負うだろう」
そうは思いながらも、私も家族も、このままでいいのか…
どう対応するのが「正しい」のか、本当に悩みました。
お休みが続けば、
息子が「本当に行けない」のか「安易に休んでいる」のか
疑心暗鬼に。
頭では分かっている…
きっと息子は怠けてるわけじゃない…
でも、本当に…?
私は甘やかしてるだけなのでは?
「行きたくない…お休みしてもいい?」
そう毎日続けて聞かれると
「わかった。でも、ずっと行ってないとお友達に忘れられちゃうから、明日だけは頑張って行こうね。」と
気付けば、息子が「頑張っていない」ことを前提に、言葉にしていました。
葛藤の日々。
そんな1年生の7月のある日、一週間ほどのお休みが続いたのち、
「今日は頑張って行こうか」と一緒に校門前まで手をつないで歩きました。
校門の前に着くと息子は立ち止まって私の方に向き直り、
そして、私の顔を見つめたまま、大粒の涙をボロボロとこぼし始めました。
普段は大人っぽいところのある子です。
そんな息子が、多くの子供たちに囲まれるなか、延々と涙をこぼし続けました。
その息子の姿をみた瞬間、
筋痛性脳脊髄炎という病で思うように日常生活を送れなくなった、
20代の自分が走馬灯のように蘇りました。
「なんでこんなことができないんだろう。」
「もっと頑張りたいのに…頑張れない。」
泣いている目の前の息子は、自分を責めて苦しんだ「過去の私」そのものだったのです。
それからは、その時の自分が「周りにどうしてほしかったか」を考えて息子に接するようにしてきました。
—————————————————————
【まとめ】
私自身の経験によって、息子の気持ちのほんの一端を知ることができたのは、
親としてただ幸運なだけだったのだと思います。
誰しも、相手の痛みを知ることはできません。
それは親と子であっても、同じことです。
そして、親は「理解してあげられない」からこそ、悩み、苦しみ、葛藤をします。
また、親子関係も、親と子それぞれの性格も、状況は様々。
不登校児の親として出発し、多くの不登校のお子さんをもつ保護者の方々と関わるうちに、
実情は、私が考えているよりも深刻であるということに気付きました。
まずは保護者の方々の肩の荷を少しでもおろすことが、極めて重要です。
そうして初めて、子どもたちの心のケアができると思っています。
Mirai.αは、子どもたちに様々な興味深いレッスンを提供することで、
保護者の方々にも、少しの間、ホッとできる時間を。
また、保護者専用のカウンセリングの機会や無料トークルームなどを開設していきます。
10年後「Mirai.αがあって良かったね」と言っていただけるようなフリースクールを目指し、
スタッフ一同、研鑽を積んで参ります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Maru.